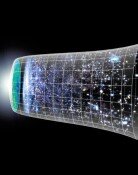1972年、ドイツのミュンヘン・オリンピック。世界中の注目を集めたなか、パレスチナ武装組職の「黒い9月」が、イスラエルの選手団11人を殺害するというテロが発生する。イスラエルの機密情報機関「モサド」は、事件の背後にいると見られたパレスチナ人のゲリラ11人を暗殺する目的で、元モサドの秘密要員アフナー(エリック・バナ)をリーダーとする5人の暗殺チームを構成する。アフナーは、ターゲットを消していくにつれ、殺人に対する罪責感と報復の正当性について悩み苦しむ。結局、暗殺チームのメンバーも正体不明の組職によって一人ひとり命を失っていく。
ストーリーだけを見ると、映画『ミュンヘン』は、手に汗握るアクション・スリラーと想像させる。しかし、スピルバーグ監督は、時間を圧縮して事件をはやく進行させる代わりに、緊迫した瞬間、瞬間の時間をゆっくり流れるようにした。
この映画は、映画的には効率的でないように見えても、実に人間的な登場人物の姿を惜しみなく見せてくれている。パレスチナ人のテロリストたちはテロを行ったが、むしろ恐怖におびえ、偶発的に行動していく。アフナーが率いる暗殺団は、引き金を引く人を決めることすらできず、くじ引きをするほどの「まとまりのない」姿だ。
そのうえ、アフナーの暗殺団を構成する逃走専門家スティーブ(ダニエル・クレイグ)、爆弾専門家ロバート(マチュー・カソヴィッツ)、後始末の専門家カル、偽造専門家ハンスなどは、自分の分野の専門技術をうまく見せるようなこともなく、支離滅裂でただ右往左往していると言ったほうが近い。映画全体に流れるこのようなリアリティと偶発性は、殺害とテロの瞬間が実際に見せる以上に、無惨に感じさせる心理的な増幅効果をもたらしている。
暗殺団が料理や食事をし、熟考する場面を繰り返し見せ、テロの背後にいる人物のことも分かってくると、妻の小言など聞きたくもないといったような平凡な人物であることを表わしている。この映画は、「やつらを片付けろ」という単純明瞭な命令のため、人々が到達しなければならない苦しい終着駅であるを見せつけているのだ。「報復」ではなく「殺人」だけが残る中東の醜い現実なのである。
ところで、この映画について、このような質問を一度してみようか。「スピルバーグの自己否定を、果たして観客は望んでいるのか」と。
スピルバーグという名前を信じて、映画館を訪れる観客が当惑するような「事態」は、スピルバーグが当初から意図した公算が大きい。しかし、欧州12ヵ国で撮影したこの163分の大作を見ている間、押し寄せる感動が、どこかで体験したような既製服のような感じがしてくる。さらにそのうえ、映画における主張やメッセージの実質に比べて、映画的なボリュームが必要以上に大きいことからくる退屈感までを、製作者側は意図していなかっただろう。
成功した商業映画の巨匠たちは、時には「他人」ではなく「自分」のための映画を撮る。それは意味深長なことでもあるが、また、不親切なことでもあるのだ。『ミュンヘン』9日上映。15才以上観覧可。
sjda@donga.com