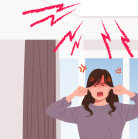今月4日に公開された映画「キャロル」(18歳以上)は、レズビアンについて公に話すことすら難しかった時代、世の中で最も弱々しく、孤立した二人の女性が運命的な恋に落ちる物語だ。
テレーズは写真に才能があるが自信がなく、彼氏との関係でも自分の意見が言えない。キャロルは自分のアイデンティティーを抑えて生きてきたが、結局夫に離婚を告げたばかりだ。その時代、女性が女性を好きになることは二重の苦難だった。二人は一緒に昼食を食べ、自宅を訪れ、ようやく全てを捨てて旅立つが、結局現実という壁にぶつかってしまう。
映画は二人がホテルのコーヒーショップで再会するシーンから始まり、再びそのシーンに戻る。二人の感情は「本当に不思議な人ね、あなた。まるで空から落ちてきたかのよう」「(お互いに好きになることは)まるで物理学のようなもの。ぶつかり合うピンボールのように」のような詩的なセリフと共に次第に増幅する。そして、最後のコーヒーショップのシーンで、単純かつ的確な文章で爆発し、観客を虜にする。
映画「太陽がいっぱい」の原作小説を書いた女流ミステリー作家、パトリシア・ハイスミスの小説「ザ・プライス・オブ・ソルト」を原作にしており、繊細で緻密な心理描写は映画の終わりまで緊張感を持たせる。
二人の女優、ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラがいなかったなら、映画の説得力は薄れたかもしれない。エレガントでがむしゃらだが、不安を抱いているキャロルに扮したブランシェットは、男女を問わずだれでも一目で心を奪われるほど圧倒的な魅力を持っている。
米国の写実主義画家エドワード・ホッパーの絵画を連想させる強烈でわびしい画面、クリスマスキャロルと一緒に流れる暗いピアノ旋律、時代を反映した衣装が、真冬のメロドラマの最後を飾る。
이새샘기자 イ・セセム記者 iamsam@donga.com